レゲエ界に革命を起こしたリズム「スレンテン」は日本人女性が生み出した:カシオ開発者・奥田広子さん

スレンテンのルーツはカシオトーンの音源
ジャマイカのシンガー、ウェイン・スミスの『Under Mi Sleng Teng(アンダ・ミ・スレンテン)』は、レゲエの世界に革命をもたらしたと言われる。友人のノエル・デイヴィーと2人で、カシオの電子キーボードを使って作曲したダンスホール・レゲエだ。1985年に大ヒットすると、デジタル音の心地よく、常習性のあるリズムは、またたく間に世界中に広がっていく。
レゲエでは、ドラムとベースのリズム体を「リディム」や「バージョン」、「オケ」などと呼び、これを繰り返すことで曲に鼓動を生む。同じリディムで複数のアーティストが曲をリリースするのも特徴だ。曲名にちなみ「スレンテン」と名付けられたリディムは、次々と新しい曲を生み出し、その数は通算450曲にも及ぶという。その影響でレゲエ界にデジタル革命が巻き起こり、ダンスホールの隆盛を生んだことで「モンスター・リディム」とも称される。
リリースから35年以上が経過した今、スレンテンの生みの親は、ウェイン・スミスや発売元のレーベル「ジャーミーズ」だと定着している。しかし元々は、1981年に発売した「Casiotone(カシオトーン) MT-40」に入っていたリズムパターンだ。スミスらは、そのプリセット音源を鳴らして、曲に仕上げたのである。

定価3万5000円で発売された「Casiotone(カシオトーン) MT-40」。写真は奥田さんの私物
つまり、電卓でおなじみのカシオ計算機が、世界の音楽シーンを変えたのだ。しかも、カシオトーンに組み込まれたリズムパターンを作曲し、スレンテンを生み出したのは、入社1年目の女性開発者だった。
そのことは、一部の音楽マニアの間でのみ、伝説のように語り継がれていたが、これまで詳細なプロフィールが公開されることも、顔を出して取材に応じたこともなかった。MT-40の発売から40年を経て、開発者・奥田広子さんが初めてベールを脱ぎ、インタビューに答えてくれた。
新入社員がいきなり任されたMT-40のリズムパターン
世界初のパーソナル電卓「カシオミニ」(1972年)、世界初の名刺サイズ電卓「カシオミニカード」(78年)と、70年代の"電卓戦争"をリードする存在だったカシオが、80年1月、スピーカー搭載の電子キーボード「Casiotone 201」を発売。楽器業界に参入した。
奥田さんがカシオに入社したのはその3カ月後。新人研修を終えるとすぐに、MT-40のプリセット音源の制作を任されたのである。

カシオ本社のショールームに飾られる電子楽器第1号の「Casiotone 201」。29種類もの楽器の音を奏でることができる
カシオは自動伴奏機能付きの商品を開発中だったが、商品化が実現するまでの "中継ぎ" 商品 として、ミニ鍵盤キーボードにリズムパターンを搭載することになったという。奥田さんは「開発部の音大出身者は、新卒の4人だけ。しかも、みんなクラシックが専門で、ポピュラーミュージックに明るいのは私だけだった」と振り返る。
当時はMIDIという統一規格もなく、デジタルの音楽制作環境が現在のように進んでいない。楽譜をプログラムコードに変換し、それを焼き込んだROMを専用の機械に差し込んで、初めて入力したリズムパターンを聴くことができた。手間と時間の掛かる作業を、完成までには何度も繰り返すため、外部の作曲者などに発注するのは難しかったのだ。

取材はカシオ本社で行ったが、普段は羽村技術センター(東京都羽村市)で開発にいそしむ
レゲエに没頭した大学時代、カシオとの出会い
奥田さんは、子どもの頃からピアノを習っていたが、中学時代に全盛期だったブリティッシュロックに目覚め、後にレゲエにはまっていく。「レゲエは、ヒップホップやラップ、DJなどのルーツとも言われ、ブリティッシュロックにも大きな影響を与えていた。何よりも、メッセージ性の強い重い歌詞を、いとも軽やかにさらりと歌ってしまうことに引き込まれた」という。
音楽高校を卒業後、国立(くにたち)音楽大学に進学。演奏家を目指すのではなく、あらゆる音楽のベースとなる楽理(がくり)を専攻し、音楽史や社会学、作曲の基礎となる和声などを学んだ。それでも、あくまでも研究対象はレゲエ。当時の日本の音大は、クラシックを専攻する学生がほとんどで、奥田さんは異色の存在だった。「卒論のテーマもレゲエ。指導教官がいなかったので、バロック専門の教授に無理やり読んでもらい、『文章的には問題ないね…』と無事卒業できた」と笑う。
卒論に取り組み、レゲエを聴きまくっていた1979年、ボブ・マーリーが最初で最後の来日を果たしている。公演会場に何度も足を運んだ奥田さんは、その少し後に、カシオが初めて音大に出した新卒社員募集に目を留めた。「開発者募集」の文言が魅力的だったのだ。面接試験の際に見せられた発売前のカシオトーンの初号機は完成度が高く、電子楽器に大きな可能性を感じる。そして、決め手となったのは、世界市場を視野に入れた、その理念だった。
楽器部門を率いたのは、創業者の樫尾四兄弟の次男・俊雄氏。計算機の発明家として知られ、楽器にも造詣が深い俊雄氏は、「すべての人に音楽を奏でる喜びを」というスローガンを掲げていた。楽理を学び、洋楽に親しみ、楽器開発への興味も強かった奥田さんは、自分にぴったりの仕事だと確信する。

入社半年足らずの奥田さん。この直後にMT-40の開発に携わる(本人提供)
リズムに込められた思いと開発秘話
入社すると間もなく、プリセットの音源制作の仕事が始まった。rockやpops、sambaなど6種類のリズムパターンと、それぞれメジャーとマイナー、セブンスの3つのコードタイプに応じたベースラインを作り、曲調の変わり目などに変化を付けるフィルインも2種類追加した。
スレンテンは、rockとして作曲したリズムだ。それがレゲエの世界で流行した理由を、奥田さんは「当時、頭の中はレゲエ一色。ロックのリズムを考えながら、自然とレゲエに通じるものになったのだと思う」と説明する。
この時代には機能や音数に制約が多く、プリセット音源に使えたのはドラムとベース音のみで、長さも2小節。ドラムに変化を付けるのは難しいため、いかにベースラインを仕上げるのかがポイントだった。

プリセット音源の操作部分。スイッチの数にも制約があるため、その仕様にも苦労したという。ノエル・デイヴィーは作曲時に「一度、リズムを見失った」と語っているが、再生までの操作が少し複雑なせいだろう
コアな音楽ファンの間では、スレンテンの元ネタは、エディ・コクランやセックス・ピストルズだという説が広まっているが、奥田さんは否定する。「ブリティッシュロックを聞いていたので、インスパイアされた曲があるのは確か。でも、それとも別物の完全オリジナル」と付け加える。
レゲエのリズムは特に意識していなかったが、「トースティングが乗せやすいように」とは心掛けたという。レゲエのトースティングとは、リズムに乗って語り掛ける行為で、ラップやDJスタイルに大きな影響を与えたもの。あまり音を詰め込み過ぎないように単純化したことで、アレンジがしやすく、レゲエ独特のコードパートも入れやすかったのだろうと奥田さんは推測する。
スレンテン・ブームを知るが、仕事に没頭
カシオの楽器事業は滑り出しから好調で、新商品を出せば世界中でドンドン売れた。常に複数の開発案件を抱えていた奥田さんは、「とにかく忙しかった」ため、レゲエとも縁遠くなっていく。営業部から「MT-40が中南米で人気だ」と聞いても、それがジャマイカと関係があるなどとは全く想像しなかった。
雑誌『ミュージック・マガジン』の1986年8月号を読んでいると、「スレンテンの氾濫~」と副題がついたレゲエの記事に「カシオトーンのビートが延々と続く」と書いてある。その音を文字で「ブブブブ、ブブブブ、ブブブブ、ブッブ」と再現しているのを見て、自分が産み落としたrockのリズムがジャマイカのみならず、世界の音楽シーンでブームになっていることを知った。
すぐに『アンダ・ミ・スレン・テン』のレコードを購入。「まさにカシオトーンのプリセットのリズム。ある程度は予想していたが、曲のイントロまでフィルインの音がそのまま使われていた」と、驚いたそうだ。そして、同時に「そうだよね」と妙に腑に落ちた。
「レゲエを聴き続け、卒論まで書いた私が生み出したリズムを、レゲエの音楽と共に暮らすジャマイカの人がちゃんと見つけて、受け入れてくれた。でも、それは輸出企業のカシオが楽器開発を始め、新入社員に大役を任せてくれたから。全ては偶然ではなく、必然だったのかもしれない」

スレンテン・ブームを知った頃。勤務先の羽村技術センターで(本人提供)
奥田さんが制作したリズムが大ブームを巻き起こしたと分かっても、会社での日常に変化はなかった。「カシオ計算機」の社名が示す通り、保守本流は電子機器の開発であり、楽器部門は傍流にすぎない。特許取得は評価されても、音楽の世界に革命を起こし、文化を生み出したことが社内的に注目されることはなかった。奥田さん自身も、そんなことを気にする余裕がないほど開発に没頭。スレンテンに関する記事などを目にする機会があれば、ひそかに誇りに思うだけだった。
著作権を申告した方が良かったのではないかとの意見もあったが、「多くの人に使ってもらうことで、カシオトーンを有名にする」ことの方が大切だった。そして、世界中の人がカシオトーンで気軽に音楽に触れ、簡単にレコーディングできるようになってほしいと願っていた。最近でも、スレンテンのオリジナルはMT-40の音源だと探し当て、わざわざカシオに使用許諾を申請する音楽関係者がたまにいる。その場合も、「自由に使っていいので、クレジットには『MT-40の音源を使用』と入れてほしい」と伝えるだけだ。
そして奥田さんは、何度も「少しでもレゲエに恩返しができたとしたらうれしい」と繰り返す。

現行の「Casiotone ミニキーボードSA-76」には、「MT-40リディム」が組み込まれており、rockのリズムパターンを聞くことができる(写真提供:カシオ計算機)
すべての人に音楽を奏でる喜びを
現在、奥田さんが開発に力を注いでいるのが「Music Tapestry」という技術。楽器の演奏の強弱や曲調を解析し、リアルタイムで絵に変換しながら、最後は1枚のアートに仕上げる。ピアノを弾いたことがない人でも、どんな絵ができるかと鍵盤に触れ、少しでも音楽を楽しんでほしいという思いで取り組んでいる。今でも創業者の「すべての人に音楽を奏でる喜びを」という理念が、奥田さんの中に生き続けているのだ。
「MT-40のリズムが世界中に広まり、いまでも愛され続けていることは、自分の子どもを産んだことに匹敵するぐらいの喜び。最初に生み出した子の出来が良すぎたので、なかなか超えることができてない。でも、電子楽器が演奏者を助けられることは、まだまだあるはず」
奥田さんは新しい音楽文化を生み出すため、開発者人生を歩み続けるようだ。
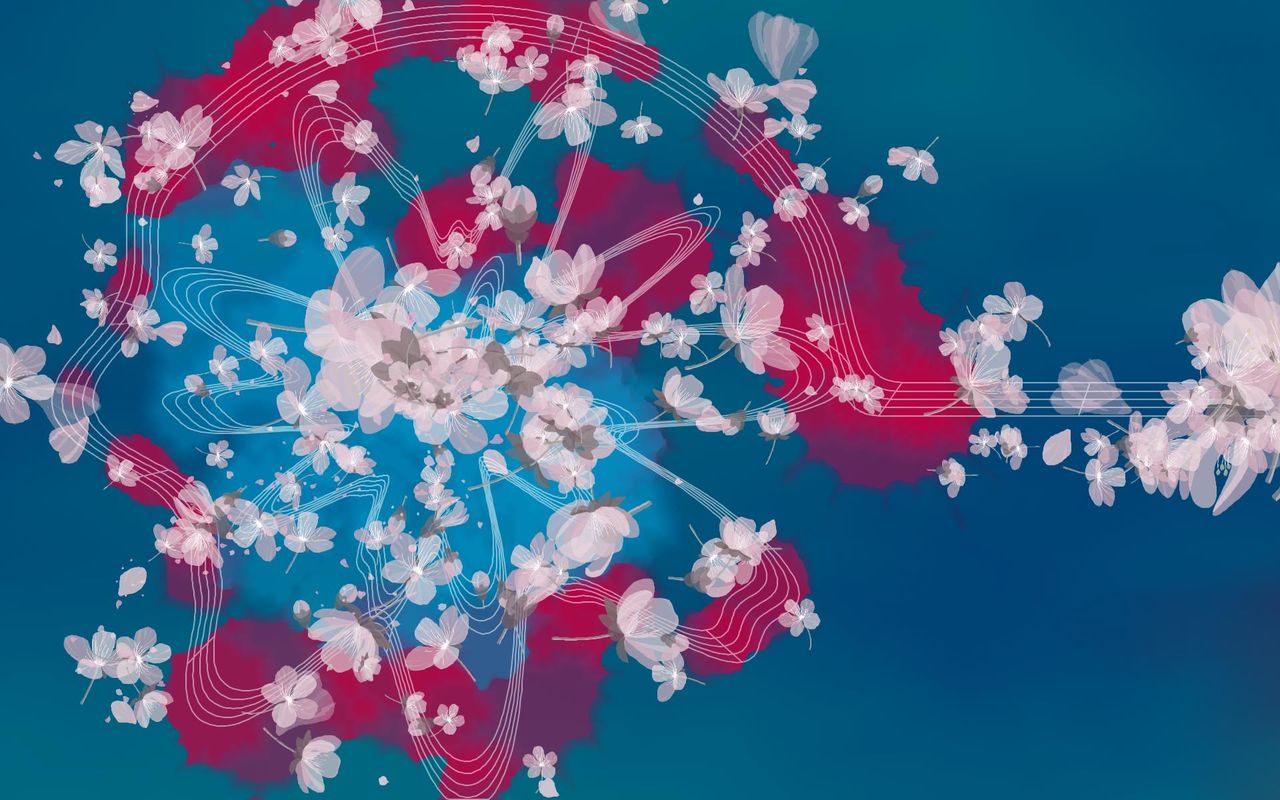
Music Tapestryのデモ演奏後に生まれたアート作品。公式インスタグラムでは、多彩な作品が見られる(写真提供:カシオ計算機)
写真・動画=ニッポンドットコム編集部




0 件のコメント:
コメントを投稿